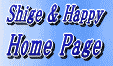 |
|||||
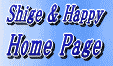 |
|||||
| ラジオ少年の頃 | アマチュア無線開局の頃 | 無線局の再開 | 現在の機器構成 |
中学生のころアマチュア無線をしている友人がいて,中学生時代から高校生時代と 友人のシャック(無線設備)に遊びに行っていろいろなことを教えてもらった。それで, 自分もアマチュア無線の免許を取りたいと思うようになった。 1969年、大学浪人をしていた時に,電話級アマチュア無線技師の免許をアマチュア 無線連盟の講習会で取得した。約10日間ほど私立の工業高校であった講習を受け 修了試験をパスすれば合格というものであった。 この頃はトリオの9R−59Dなどのメーカー製の無線機もあったが,古いラジオを分解して 得た部品で作った自作機で交信するアマチュア局も多かった。電信級の免許を持っている 人は,もっぱら,トン・ツーのモールス信号による交信を楽しんでいたようである。 電話級の方はまだAM(振幅変調)の交信も多く,自作派もそれなりに楽しむことができた。 周波数帯は,10Wの出力でも日本全国と交信できる7Mhz(メガヘルツ)が中心であった。 私自身も,開局した時は自作の真空管式の送信機と受信機であった。送信機の終段管は 最初のころは友人にもらった中古の807,あとでS2001に替えた。受信機は俗に「高1 中2」と言われる,高周波1段増幅,中間周波2段増幅型の受信機であった。 自作にあたっては「初歩のラジオ」や「ラジオの製作,「CQ」などのラジオ雑誌が大いに 参考になった。キットを組み立てるのではなく,アルミのシャーシに穴を空けるところから 自作するわけだから,今から考えると相当の手間ひまかけてのことだ。 苦労して配線まで終了して,電源を入れるときの緊張感がまたたまらなかった。時には 抵抗の焦げてしまったり真空管のプレートが赤くなって熔けかけたりと失敗もあったが, そのような苦労のあとで,スピーカーから交信が聞こえてきたり,こちらの呼びかけ(CQ) に,相手が応答してきた時などは本当に感激の瞬間だった。 アンテナは逆L型のワイヤーアンテナを自宅の屋根の上に張っていた。電灯線用のビニ ールコードを水平に張っただけの安上がりのアンテナである。 そのうちに、7Mhz帯だけの運用にあきたらなくなり,144MhzFM(周波数変調)のメーカー 製トランシーバーを購入した。トリオのTR7200?だったろうか,記憶違いかも知れない。 その頃の144Mhz帯は呼び出し周波数が144.48Mhzだったように思う。現在は145.00Mhz になっている。このトランシーバーは就職で離島勤務になったときにも持っていき,職場の 屋根に7エレほどの八木アンテナを上げて交信していた。 しかし,その後有効期限5年間の無線局の免許状の更新を怠り、無線の世界からもずっと 遠ざかってしまった。 |